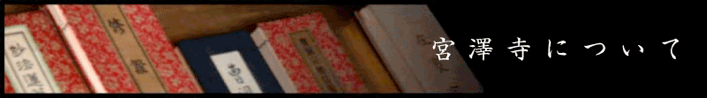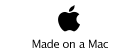地域に合わせて堂宇完成 平成23年7月
宮澤寺は、江戸時代前期(1632年)、東顕寺六世・崇岳善寿大和尚によって開創されました。当初、地名にちなむ「本野山」の山号でしたが、いつのころか、今のように改めています。
歴代住職中、3人の中興の称号があるので、本堂建て替えなどの大事業のときと推量されますが、昭和22年に再度の火災に遭い、文献等を焼失しました。また、古い仏像や什器なども、重なる火災により現存していません。
平成23年7月盛岡南新都市開発事業に合わせて近代的な本堂と位牌堂を完成致しました。
お年寄りや障害のある方のためにリフトやエレベーター等を完備し室内はバリアフリー(段差の無い)になっており、車椅子も完備しております。
宮澤寺の境内地には、墓相学の大家の指導による無縁塔があり、山門の内側には、地蔵菩薩を中心に300余の墓石が安置されています。
この間、住職は、墓地整備に力を注ぎ、雨天のお参りにも困らないよう全面舗装とし、外灯と水道を備えました。同時に、墓数も多いことから墓地名簿を整え、遠来の参拝者でもすぐ探せるよう一覧化しています。
地名に残る往古のようす
宮澤寺の寺号は、所在地の本宮字宮沢からとったとみられています。
この地は、志波城跡や大宮神社に近く、古い歴史を秘めた土地柄といえます。
本宮の地名は、往古、お宮があった地に由来するといわれますが、宮沢の地名にも言い伝えがあります。
その昔、このあたりは大小の支流がながれ、めくら川といわれていました。雫石川の左岸に建つ天照寺(天昌寺)と、右岸の熊野神社(現在の原敬記念館付近)の眺望を、京都の落人たちは、雫石川を賀茂川、南昌山を東山になぞらえて故郷をしのび、月見の場所にしたといわれています。
そして、熊野神社の沢のところから付近一帯が「宮沢」に、熊野神社付近が「熊堂」の地名になったということです。